| |
|
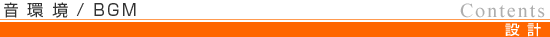 |
| |
日常、生活の場においてあまり関心を持たないものは、音のようです。関心を持つ、というよりも音に対して注意が向く場合、それは交通騒音であったり生活騒音であったり、不快感を抱くときの方が、心地よい音に包まれるときよりも多いようです。当社はここに着目し、良い音場を形成するというよりむしろ、不快感を削除する音場を形成するための設計を行っています。
[サウンドスケープの概念と理論を、現場レベルで臨機応変に実践する、といったイメージです。]
不快感の定義は、個人差があるとしても、さほど差異はありません。しかし、良い音場というのは個人差があります。音楽にしても好きなジャンルであればBGMとして最適ですが、嫌いなジャンルであれば騒音になることも少なくありません。そしていくら好きなジャンルとはいえ、例えば不必要なタイミングでその音楽を聴いていれば、それも騒音になってしまったりするものです。
ここでは、当社の音環境整備に伴う考え方を記載します。実際にその場で計測したりしなければ詳細は得られませんが、このサイトをご覧の皆様が、この項目をご覧になり実践され、少しでも快適な空間を構築できれば幸いです。良く分からない、というときは、お気軽にご相談ください。 |
| |
| BGMによる空間演出 |
BGMとはバックグラウンドミュージック(Back Ground Music)であることはご周知のことですが、近年ではこのミュージックがサウンドという言葉にかわったものもでてきています。総称してBGMではありますが、例えば滝の音や鳥のさえずりといったような、環境音などのサウンド物がそれにあたります。これらの発想はもちろん悪い価値観ではありません。しかしながら、利用方法を熟慮しない限り、場違いなBGMとして空間選出には不向きな面を露呈してしまうことになりかねません。実際そういう演出をしているところも多いものです。音によって感じ取る雰囲気が左右されやすいことを常に念頭に置き、BGMを選択することが大切になります。
大切なのは、BGMを使ってどういう雰囲気に仕立て上げたいのか、第三者にはどういう雰囲気に感じてもらいたいのか、という部分になります。演出をする側のスタイルを全面に出したいならば、第三者のことは二の次でも構わないでしょう。しかし、第三者(店舗であれば来客者、事務所であれば従業員など)のことを第一に考えるならば、BGMを採用する事前に、聞き取りなどの調査をすることが大切になります。また、定期的に同じ曲を選択し、時刻の合図や売上状況などを示唆するような使い方も効果的です。色彩設計などとも同様な考え方です。
理論的に感情をコントロールする選曲は可能です。詳細をお知りになりたい方は、“お問い合わせフォーム”よりお問い合わせください。 |
| |
| 空間種別による音環境の整備について |
かなり大まかに空間種別を取ると、屋内と屋外になります。ここでは大きく分けて屋内の音環境のあり方と屋外の音環境のあり方を、空間演出という点をプランニングデザイナー(調査/企画/デザイン)の見地より考察します。
屋内で効果的な音環境を構築するには、屋内の使用目的により残響バランスを取ることが基本となります。 事務所であっても、電話オペレータの多いような会社から、図面や画面とにらめっこをし続け会話のかなり少ない会社まで、また商業施設であっても、威勢の良い売り子が多いスーパーマーケットから、ハンガーの擦れる音が聞こえるほど静かなブティックまで、用途目的などにより大きな差異があります。
音は視界に入らない部分のものまで感知されます。そのため、視界からの情報が左右する感覚に音を重ねてその情報を増幅させるのか、その逆で音によりその情報を減衰させるのかを選びます。
|
| 視界情報 |
静かなイメージにリフォーム |
賑やかなイメージにリフォーム |
| 会話の多い
事務所 |
残響を抑える資材の多用 |
区画ごとの音源と音圧のバランス維持 |
| 賑やかな
商業施設 |
音源数を必要最低限で設定 |
明るさと規律性を持つ構成の音楽をBGMに採用 |
| 会話の少ない
事務所 |
明るくても落ち着いた構成の音楽をBGMに採用 |
明るさと賑わいを持つ構成の音楽をBGMに採用 |
| 静かな
商業施設 |
明るくても落ち着いた構成の音楽をBGMに採用 |
明るさと賑わいを持つ構成の音楽をBGMに採用 |
|
※この表はあくまでも参考例です。BGMの選定も、理論に基づいた構成の楽曲が必要です。
|
屋外での効果的な音環境とは、その空間の定義で大きく異なってきます。例えば大型の駐車場や商業区画としてのスペース、観光地などであれば、それはある意味、屋内の賑やかな商業施設に対し特異性はないでしょう。公園や庭園など、憩いの空間として存在させたい部分であれば、屋内での静かな空間を必要としている部分に類似する部分も見受けることができるでしょう。
これらを総合的に分析し、企画デザインをすることで快適な空間を演出することが可能となります。環境はひとつではないので、かなりのパターンがあり、それぞれに個性や特徴があります。それをひとつひとつに対応させ、丁寧に構築していくことが大切になります。
騒音対策の諸設計は、細やかな測定から防音施工まで、幅広く行います。有限会社マキノデザイン代表取締役が九州大学芸術工学部(旧/九州芸術工科大学)音響設計学科卒業ということもあり、調査研究として大学及び関連企業との連携も可能です。
本サイト“色彩/照明”もご覧ください。音環境の構築はそれ単体でももちろん効果はありますが、聴覚情報に加え視覚情報もリニューアルさせることで、空間の演出はとても豊かになります。 |
| |
|
| |